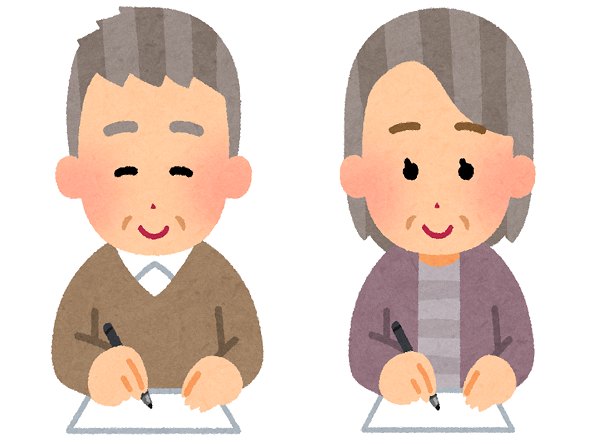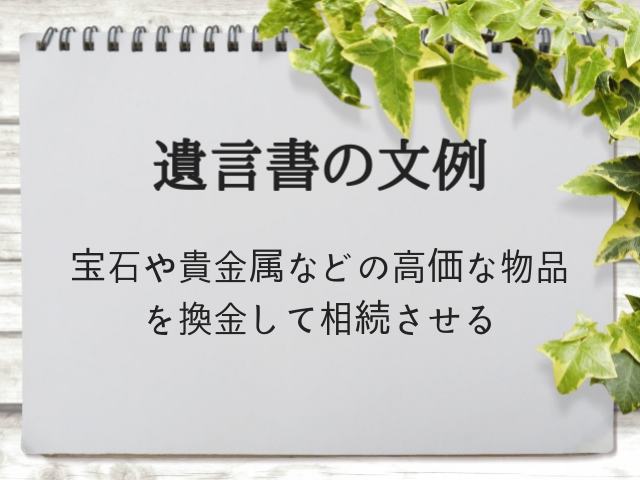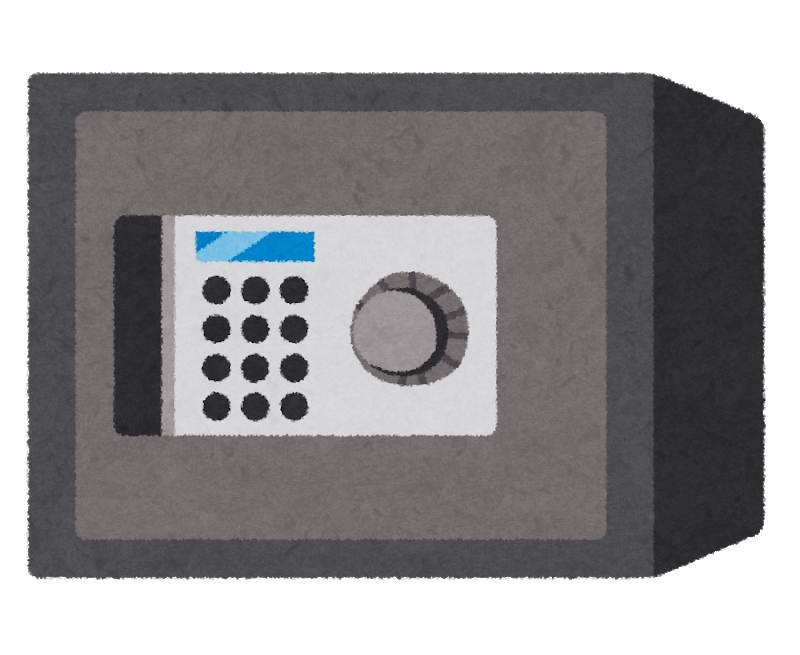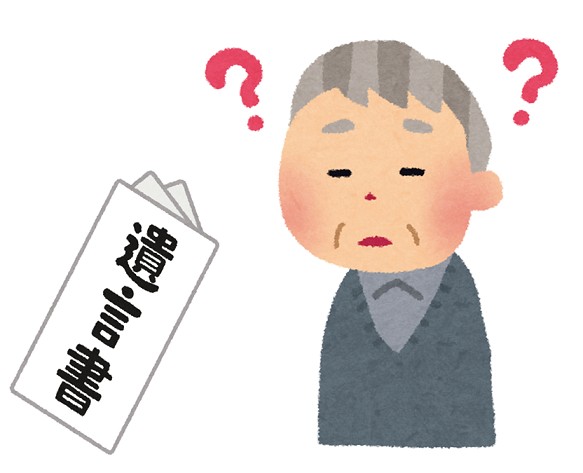
認知症になると、しっかりと意思表示をしたり、高度な判断を要する法律行為を単独でするのが難しくなるため、遺言書を書くという行為も難しくなってしまいます。
そのため、できれば認知症になる前に、遺言書を書いておきたいところですが、いつ認知症になるかなんて誰にもわかりません。
この記事では、認知症患者にも遺言書は書けるのか?という点から解説していきます。
- 認知症の方が書いた遺言の効力について
- 成年被後見人が遺言書を作成できるケース
- 医師の診断書、公正証書遺言作成の重要性
認知症の方が書いた遺言は無効なの?
遺言を有効に作成するためには、遺言者に「遺言能力」がなければなりません。遺言能力とは、「遺言をするために必要な、行為の結果を弁識、判断しうるに足りる意思能力」とされています。
つまり、簡単に言いますと、遺言を書いたことで、その後どのような結果となるのかを、遺言を書く当時に理解できていなければ、遺言能力がないことになるのです。
民法963条に次のとおり規定されています。
第九百六十三条 遺言者は、遺言をする時においてその能力を有しなければならない。
(出典:e-gov-民法)
遺言能力がない方が書いた遺言は無効です。
では、認知症を罹患されている方が、すべて一律に遺言能力がないとされるのかと言えば、そうではありません。
例えば、まだら認知症の方で、立ち合いの医師や公証人との対話状況などから、遺言作成時の遺言能力を認めた事例もあります。
また、軽度の認知症の方で、遺言作成時に遺言能力があった旨を医師が診断書などで証明してくれた場合なども、遺言が有効となる場合もあります。
上記のように医師や公証人が遺言作成に関係した場合は、その証言を利用することもできるでしょう。
ですが、1人だけで作成できる自筆証書遺言の場合には、遺言作成時に遺言能力があったことを証明するのは難しいと言えます。
後見開始の審判を受け、成年被後見人になるという選択
認知症も重症化すると、単独ではしっかりとした意思表示をすることが難しくなります。そして、法律行為についても、行為の結果どうなるのか、自分にとって得か損かを判断することも難しくなるでしょう。
このような状態で法律行為や財産管理を単独で行うのは危険であり、本人にとって大きな損失をもたらすおそれがあります。
上記の理由から、家庭裁判所は判断能力を欠く者のために後見開始の審判を行うことができ、後見人が選任される仕組みがあるのです。
後見開始の審判を受けることで、認知症を罹患していた者は「成年被後見人」となり、「後見人」が選任されます。
成年被後見人の締結した契約は取り消すことができるなど、法律で保護されるので、認知症と診断された方は、後見開始の審判の申立てをされることが望ましいです。
関連する条文が民法にあります。
(後見開始の審判)
第7条 精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者については、家庭裁判所は、本人、配偶者、四親等内の親族、未成年後見人、未成年後見監督人、保佐人、保佐監督人、補助人、補助監督人又は検察官の請求により、後見開始の審判をすることができる。(成年被後見人及び成年後見人)
第8条 後見開始の審判を受けた者は、成年被後見人とし、これに成年後見人を付する。(成年被後見人の法律行為)
第9条 成年被後見人の法律行為は、取り消すことができる。ただし、日用品の購入その他日常生活に関する行為については、この限りでない。(出典:e-gov-民法)
※後見開始の審判について→家庭裁判所HP
成年被後見人でも遺言書が書ける場合
成年被後見人であっても、条件を満たせば遺言を書くことはできます。
民法に次のとおり規定があります。
(成年被後見人の遺言)
第973条 成年被後見人が事理を弁識する能力を一時回復した時において遺言をするには、医師二人以上の立会いがなければならない。
2 遺言に立ち会った医師は、遺言者が遺言をする時において精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く状態になかった旨を遺言書に付記して、これに署名し、印を押さなければならない。ただし、秘密証書による遺言にあっては、その封紙にその旨の記載をし、署名し、印を押さなければならない。(出典:e-gov-民法)
つまり、成年被後見人が遺言書を書くためには、判断能力が一時的でも回復していること、それを医師2人以上が証明すること、が必要なのです。
なかなか難しい条件かもしれません。しかも重度の認知症であり、判断能力が回復するときなんて全くないような状況では、遺言は書けないということです。
判断能力の有無を診断するのは難しい
民法上は上記のように決められていますが、実際に判断能力が一時的に回復していることを証明するのは難しいようです。そのためか、病院によっては、この証明を拒否するところもあるようです。
対策として、主治医(かかりつけ医)に相談する、片っ端から病院に電話をかける、という方法が考えられます。
できれば認知症になる前に遺言を書く、それが無理でも症状が軽いうちに後見開始の審判を受け、医師の証明のもと遺言を書く、というのが望ましいでしょう。
対策:公正証書遺言を作成する、医師の診断を受けておく
認知症の疑いがある方について、一番危険なのは、お一人で作成できる自筆証書遺言を作成されるケースかと思います。この場合、医師も公証人も関わらないため、認知症でなかったことの証明ができません。
公正証書遺言であれば、公証人と対話しつつ作成していくので、その遺言能力については、完全でなくとも一定の保証がなされます。
さらに、認知能力について不安な方は、医師の診断を受けておき、遺言作成時に遺言能力があった旨を証明できる診断書があれば、心強いです。
いずれにしても、判断能力が衰えていない元気なうちに作成されることが一番望ましい方法ではあります。
簡単な遺言内容に止めるという選択肢もある
遺言書の作成当時に、遺言能力がなかったと裁判で争われることがあります。その場合、遺言書に記載された事項の複雑さが判断の基準になることもあるのです。
例えば、「妻に全財産を相続させる」というような比較的単純な遺言もあれば、「複雑な株式の配分計算を含む事項」のような複雑な遺言もあります。
遺言能力が争いとなったとき、本人にどの程度の判断能力が残っていたかにより、有効になる遺言、無効になる遺言が出てきます。
そのため、自身の判断能力に不安を覚える方は、比較的簡単な遺言内容に止める、という選択肢もあるのですね。
まとめ
認知症患者でも遺言書が作成できるのか、という点から解説してきました。本来遺言書とは将来に備え、元気なうちに作成するべきものです。遺言書について、死期が迫った際に作成するもの、という誤った認識の方が多いと言えます。
自身の判断能力に不安な方は、医師の診断を受け、できれば公正証書遺言を作成されることをお勧めします。
要チェック! 相続、遺言の基礎知識まとめ(カテゴリーごとに解説します)
相続、遺言について深く学ばれたい方はぜひご確認ください。